
幼児期に大切な2つのこと
幼児期の達成感と2つの大切なこと。親からの愛情と自己肯定感を幼児期に確立することがとても大切です。

幼児期の達成感と2つの大切なこと。親からの愛情と自己肯定感を幼児期に確立することがとても大切です。

子どもは楽しいことしか取り組まないので、楽しく本能的に感じる音楽が伸ばす!

お母さんと子どもの関係。親子の絆、スキンシップ、愛情、乳幼児期が大切!

子どもの脳は3歳までに80%完成される!乳幼児期に良い刺激、楽しい刺激、親からの愛情をどう受けたかで子どもの人格が決まる! 楽しいと本能的に感じる「音楽」が最適!
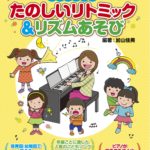
子どもと音楽を楽しみ伸ばせるリトミック!親子で気軽に音楽で楽しめる書籍と動画のご案内!シンコーミュージック/「らくらく指導たのしいリトミック&リズムあそび」


千葉市若葉区 子どもの才能が開花するリトミック 加山佳美です。 私は音楽教室でピアノとリトミックを指導しています。 ...