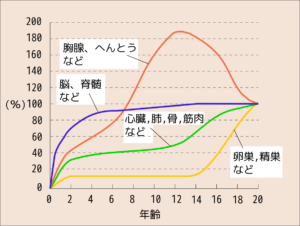幼児の特質
子どもは楽しいことしか取り組みません。
成長過程での特質で、
全てが「あそび」だと思っているからです。
靴をはく
食事をする
お片づけをする
など
大人から見ると
すぐふざける~
と感じる場面・・・
子どもはあそびながら学んでいます。
つまり、
「楽しいこと」には集中する
ということ。
年齢に合わせた楽しいこと
そして、オススメなのが、
「年齢や発達に合わせたこと」のちょっと先のできること
を環境として与えると成長が伸びます。

この様に「楽しいこと」しか取り組まない「幼児の成長」にぴったりなのが
「音楽」なのです。
「音楽」は本能的に大人でも誰もが心地よいと感じます。
カフェや歯科などで 心地よい音楽がかかっていますよね。
そして、音楽は多彩です。
(色々な音楽があるということ)
聴覚に優れている幼児は
多彩な音楽を聴き分ける能力を持っています。
そして、細かいことよりも身体全体で動くことを好みます。
これも発達上の特質。
テレビやショッピングモールで流れてくる音楽に乗って体を動かすのも
この特質のためです。
1歳だからこれしかできない
2歳だからこれしかできない
ではなく、
聴覚に優れた
赤ちゃんの年齢から「音楽」を聴き分けられるのですから、
その特徴を生かすと
1歳だからこれができる
2歳だからこれができる
となります。
「まだ早いので~」
というお母さんの知識は全く「勿体無いお話」で・・・
早い時期こそ、「音楽経験をするべき」なのです。
そして、そこに
子どもの一番大好きなお母さんが一緒にいれば
相乗効果も抜群です。
幼児の英語教室、体操教室、水泳教室に行っても
「音楽」がかかっていますよね。